
About
「quartets online」は、2020年に山口情報芸術センター[YCAM]にて制作されたオンラインアート作品です。コンピュータによってリアルタイムで生成/ストリーミング上演され続ける演奏は、インターネットを介して世界中で同時に同じ演奏を聴くことができる一方、その演奏は二度と繰り返すことなく常に新しい組み合わせで流れ続けます。
本作品は、2008年にYCAMで開催された展覧会『大友良英/ENSEMBLES』にて制作・発表された「quartets」という作品がルーツになっています。「quartets」は会場中央に配された4面スクリーンの立方体と、会場周縁に配された4面スクリーン、合計8つの映像と、立方体内部を含む合計10台のスピーカーによって構成されたインスタレーション作品で、その後、東京のNTT インターコミュニケーション・センター[ICC]、およびバンコクのアート・アンド・カルチャー・センターBACCでも巡回展示されました。
「quartets」の音源は、2008年の制作時に収録されたもので、大友によって「ソロでの演奏だが、他の演奏家の存在を想像して音を出す」よう各演奏家に指示され収録されました。つまり「想像上の他者の音とアンサンブルしているソロ」の音源ということになります。演奏家の姿を記録した映像は、アーティストの木村友紀によってディレクションされ、演奏者の背後から微妙に揺れ動く照明で照らされた影によってあらわされています。インスタレーション版では、演奏家の影は中央の4面スクリーンに常に異なる組み合わせであらわれては去っていき、8名のうち最大4名の演奏をどの順番で選択し、どのスクリーンで組み合わせるかは、アーティストの平川紀道によって組まれたアルゴリズムによって決定されていました。会場の周縁に配置された4つのスクリーンには、アーティストのベネディクト・ドリューによる映像が投影されました。正対する中央のスクリーンで演奏している演奏者の音がスピーカーを通じて木や鉄、液体を振動させている様子が映し出されていました。作品空間に入った鑑賞者は全ての音を同時に聞くことは出来ても、全ての映像を一度に見られないというのが一つの特徴でした。
今回の「quartets online」は、従来の「quartets」をインターネットを介して世界中で見られるようにしたインターネット上に存在するアート作品です。単にインスタレーションの記録映像ということではなく、演奏のアルゴリズムや映像の演出も制作し直した、オリジナルのアート作品となっています。このオンライン版の構想はオリジナル版の発表からほどなくして大友とYCAMの間で検討されていたものでした。即興演奏という表現を行う大友にとって、生身の身体によるライブ演奏や、記録媒体に収録されたレコード、CDとは異なる音楽のあり方は常に模索されてきたテーマでした。
2020年、新型コロナウイルス感染症とその社会的な対応によって多大な影響を受けた表現形式の一つが音楽です。人が集まることのできない世界において、音楽はいかに響くのか。一人一人が見えない他者を想像して演奏する「quartets」を、このタイミングでオンライン版として制作しようとアーティストとYCAMの間で合意できたのは、時代に反応し常に表現の刷新を試みる姿勢が呼応しあった結果と言えるでしょう。コンピュータによってリアルタイムに生成されストリーミングされる「quartets online」は、世界同時に即興演奏が聴ける作品であるのと同時に、オーディエンスが参与する余地の多い作品ともいえます。直接的なインタラクションはありませんが、リズムやメロディが明確に構成されず、音楽になる少し手前のような繊細な音楽が持続します。それゆえにオーディエンスが微妙な音の揺らぎに耳を傾け、組み合わせの新鮮さに驚き、印象や解釈を構築する余白をたたえています。
人と人との距離を考えざるを得ない状況の中で、この作品を通じて人々が繊細な演奏に耳を傾け、遠くの誰かを思い描くこともあるかもしれません。一つの作品が他者への想像力を後押しできることを願います。
Message from Otomo Yoshihide
2008年YCAMで3ヶ月にわたって行われたENSEMBLES展の中で生まれた作品「quartets」が、12年の歳月を経てオンライン版で復活しました。
オンライン版の構想自体は、かなり初期の段階からありました。実現しなかったのは、口には出さねど、どこかで実際のリアルな展示作品に勝るものはないと考えていたことも大きな要因です。世界中の誰もが同じ音楽聴取をすることが出来る録音作品が音楽体験の中心になった現在、それとは異なる録音作品の再生聴取の方法があってもいいのではないか。その場に来た人だけが体験し、しかも誰一人として同じ体験は出来ない……録音作品ともコンサートとも異なる音楽、この作品に関しては、そういうことでいいと考え展示作品のみにしてきました。
それでも今回オンライン版の制作に踏み切ったのは、コロナ禍の状況の中で、そもそもそうした特殊な体験をするために人々が集まることが難しい状況が最初の切っ掛けでした。制作の過程で、オンライン版ならではの不自由な条件の中で、極端に情報を切り詰める必要が生じたことで、実際の展示に比べ音楽の再生ということによりフォーカスがあたることに気がつきました。であれば、昨今ネットの中ですでに飽和状態になっている録音音源の再生による音楽聴取とは異なる方法の音楽の再生(文字どおり、再び生き返らせる)方法をここで模索できる、そうわたしは考えはじめました。いつでもアクセスできる録音音源にも関わらず、常に異なる状態でありつづけるような音楽作品。ネットの空間で始まりも終わりもなく、歳すらとることもなく、AIでもないのに永遠に即興演奏を生成し続ける録音作品。そんな矛盾に満ちた音楽再生装置。いつしか展示版とは全く異なる作品が出来上がりました。
同時に、今回の作品を作ることで、再び、この作品をリアルな展示空間に持ち込みたくもなっているのもまた事実です。多分そのときは以前とはまた異なる展示作品として立ち現れるのかもしれません。
Credits
quartets online (2020)
2021年1月12日は、サーバーメンテナンスのため、作品の配信ができません。



quartets (2008)
Talk (2020年8月12日収録)
「quartets」の作られ方
伊藤隆之(YCAMテクニカルディレクター):東京のNTT ICCと、バンコクのBACCでやりましたね。
大友:思ったほど他で展示できていなくて。今回コロナの状況になって、いろんなことがオンラインでしか展開できないという中で、このアイデアをYCAMの伊藤さんから聞いた時に、やっときた!と思いました。でも、僕の頭の中では、ずっとこの人たちは演奏し続けてたんです。ずっと見えないところでやっていたんだけれど、やっと見えるところに出てきた、みたいな感じで。自分も含めて2008年のままなので、あの時のまま止まっているのに演奏し続けているという面白い感じではありますね。
会田大也(YCAMアーティスティックディレクター):終わりをイメージしないというパターンというのは、他の作品にはないものですか?
大友:例えばコンサートだと1時間で一幕とか、始まりと終わりがある一方で、展示作品の中には始まりも終わりもない。けど、これは最初から延々と続いていて二度と同じ瞬間は訪れない、天文学的な確率では訪れるのかもしれないけど、ずっと新たに生成され続けるというイメージだった。その生成がAIとかではない、ということも面白いと思います。
会田:平川さんはどうですか。2008年と今の状況の中で、視座が違うということも含めて作品への感じ方に変化がありましたか?
平川紀道(アーティスト/プログラマー):最後にプログラムを動かして音を聞いたのは、12年ぶりですかね。今回、時間が経って、また耳にしたわけなんですが、動かした瞬間に、それこそずっと鳴り続いていたんだろうなというか、この作品の当時の記憶も含めた、作品の印象が一瞬で戻ってくる感覚がありました。時代ごとに作品の解釈や見え方が変わるってこともありますが、この作品に関しては古くならないというか、最初から古いとも言えるというか。
大友:その通りですね。
平川:YCAMでやったのがオリジナルということにはなっていますが、作品の形が実は可変であって、けれどもアイデアとしてはずっと変わらない、ずっと続いていくものというのがあるんだなと改めて感じました。
同時に見ている人を想像する
大友:最初から影を使うというアイデアがあって、そもそも影絵自体はものすごく古いアイデアですよね。
僕は子供の頃、町内会で影絵をやっている時代だったので、それも関係あるのかもしれない。影絵ではない選択肢もあったとは思うけど、それだと違う感じがしたんですよね。作り手側がコントロールできない要素もなるべく作りたいと思っているところがあって。見る人によっても、見る角度によっても全部違うようにしたいと思っていました。
元々は人間の影も等身大に近いもので、YCAMで展示した時、障害を持った子があの裏側に人がいるんじゃないかと勘違いしたことがあって、このことがものすごく嬉しかったんです。それと、展示では別々の方向に4面あるので、全部を見ることは誰にもできません。それが平面になると全部が見えてしまうわけで、そうなるとどういうふうに見えるのか、聴こえるのかってことは、最初に平川くんから送られてきた試作を見るまでは、正直実感できませんでした。
会田:音楽の根源には、祈りというか、見えない相手に対する思いとか念といったものがあるように思います。音源の収録の時に各演奏家に指示した内容を伺えますか?
大友:当時は震災もコロナも経験していないですし、祈りとか何にも考えていなかったですね。ま、経験してたとしても、そういう指示は僕からは出しません。演奏者に出した指示は、「基本はソロで演奏して欲しい。通常のソロと違うのは、他の誰かが演奏している、3人とか4人とかかもしれないけれど、誰かが演奏しているってことだけは頭に入れておいてください」みたいな感じだったかな。相手がどんな音を出すか、どんなことをやるかは全く想像しないでもよくて。単に「隙間を開けてくれ」という指示よりはそっちの方がいいかなと。本当にそれくらいでしたね。ただ、みんなお互いに知っている人たちなので、相手が何をやるかはなんとなく知っていてやっているところはあったかな。唯一カヒミさんにだけちょっとだけメロディのラインを示して、それが唯一の音楽的な指示ですね。
それをその通り歌うんではなく、間を開けてというのをお願いしたかな。多分、ボーカルというのは強いので、他の演奏が全部伴奏に聞こえてしまう気がしたので、歌になる直前の声みたいなことでやってほしいなと思って。
会田:全体として音楽になる直前の音楽という感じがします。
大友:結果的には、みんな音楽になるかならないかのギリギリの寸止めみたいなところでやってもらった感じです。でも、それすら指示はしてません。一つには他の人が演奏するというのもあったけれど、一番は見ている人の中で音楽が生まれてほしいから、演奏者の側から音楽を提示するんではなくて、演奏者はきっかけのトリガーみたいな断片だけでいい、と当時思っていたのが大きな理由です。あと作り手がコントロールしすぎないようにしようと。それで、ああいう指示になりました。他には、「演奏時間は数分から十分くらい」と伝えたけど、中には十数分も演奏していた人もいましたが(笑)。
会田:先ほどあったように、オーディエンスが最後のピースを埋めるような作品ですよね。
だから、一人で見るだけでなく何人かで一緒に見ることで、作品との対話が二重三重に豊かになる可能性もありますね。オンラインになった時でも人と見てほしいなと思いました。
大友:オンライン版はいまこれを見ているのは自分一人だけれど、世界中の他の誰かが見ているかもしれないというのは、逆にイメージできる。これはコロナ禍ではとても大切なイメージの持ち方だと思います。モニターの前に座って見ている自分は一人なんだけれど、他の誰かも同じものを見て何かを感じているのかもしれない、とイメージすることはとても大切なことかなとは思っています。
会田:月食とか日食の時に、同時に観てる人を想像するのに似てますね。
大友:下手なラブレターがよく使う手だよね。君と同じ月を見ているよ、みたいなクサイ台詞(笑)。
会田:同時に接続して、同じ演奏を聞いている人が世界中にいるかも、と想像できることは、イマジネーションの範囲が拡がりますね。
平川さんは、オンラインで同時接続になって広がりを持つという話は、技術側から見た時に思うことはありますか。
平川:この作品に関しては、特にそうした視線で見ることはないですね。けど別の視点からいうと、続いていくことが祈りに近いみたいなことをプログラムを書いている時に感じることがあって。プログラムを実行させた結果はものすごく複雑なものになるんですが、それを作り出している元のプログラムというのは、状態は違っても常に同じプロセスの繰り返し。ひたすら繰り返していくさまが祈りに近いなと感じますね。
大友:同じプロセスだけれど、見える結果が全然違う。それが面白いですよね。最初に作ったときとソフトウェア自体は結構変わっているんですか。
平川:目指していたプログラム自体は変わってないのですが、ただ今回ちょっと仕組みが変わったので、そこに手を着けて整理してもいいのかなと。2013年の巡回展示の際に物凄く直したつもりだったんですけど、今見るとやっぱり改善の余地ありっていう風に見えますね。
大友:2008年当時も永遠に続くって言ってるけど、そもそもこのMacとかのシステムがそんな永遠にあるとは思えないよねって話はしてましたよね。
会田:(笑)。確かに。
大友:絵画とかの方がやっぱ永遠なのかもしれないなってどっかで思いますよね。
伊藤:僕らは結構2年前のメディアアート作品を直すことがしょっちゅうで、全然スケールが違うなと思って。デジタル機器はフォーマットも含めて20年で大体だめになりますよね。
会田:でも、そういう意味でいうと、お祈りとか本当に口承だけで続いてきているものが1000年ぐらい続くのも凄いなと思って。
大友:そうですよね、1000年どころじゃないかもしれない。でもそういうので言うと、即興のこういう形の演奏ってそんなに古いものじゃない、この3,40年のものだと思うけど、ただ、何かの音が、何かのシステムで動くと、人は、祈りと思ったり、何か異界、他の世界と繋がってるって思う癖がどうやらあるようです。しかも暗いとその効果は増すみたい。
会田:確かに。
大友:お祭りとかやってても盆踊りなんかは昼間やるのと、夜やるのじゃ全然他所の世界との繋がり感が変わってくる。そういう意味で言うと、そこまで意識してたわけじゃないけど、音楽が何か、音楽以外のものと繋がるっていう最低限の要素を切り詰めて切り詰めて当時はあの作品に入れ込んだような気もするんですよね。シルエットだけ、音楽になる直前の音とか。何か感じ取れるような、最低限の要素を、詰め込みたかったんだろうなと。当時はね、そこまで理屈で全然考えてなかったけど。きっと平川くんならやってくれるかもって思いながら(笑)。
平川:当時の最先端の技術を用いて、めちゃくちゃプリミティブなことをやっていたなと思います。
大友:そういうことですよね。結局、最もプリミティブな、その文化とかが形作られる直前みたいなことがやりたかったのかもしれないですよね。
変わっていくもの、変わらないもの
会田:残念ながら2008年の最初の発表以降、大震災が起きたり、コロナによるパンデミックが起きたりなど、人類全体が何か、祈らざるを得ないような状況が生まれています。そこに何か新しく対処とか打開の方法、乗り越える知恵みたいなものを絞らなきゃいけなくなった。恐らく人間は、こうした未曾有のシチュエーションをどう乗り越えるかっていうところで、これまで創造性を鍛えてきたって思っているんです。この時代に「quartets」を観ると、そんなことを考えてしまいます。
大友:うんうん。なんか今は人と人が集まれないってなってるじゃない?そう言われて初めて気付いたんだけど、今だめって言われてることがほぼ音楽の本質なんですよね。密室とか、密着するとか、凄い狭い範囲でやるっていうのが音楽の本質で、それが出来ないのは、もう本当に最初は羽をもがれた気持ちでした。けど、それに対して昔だったらもう手の打ちようがなかったのが、意外と助けになったのがデジタルテクノロジーだったなと思ってて。でも、結局やることはZoomで繋げてんのに超アナログなんだよね。飲み会とかさ。でもZoom飲み会と比較したくないな、この作品を(笑)。
一同:(笑)
大友:ごめん、飲み会と比べるのはあんまいい例えじゃないかもしれないけど、でも求めるものはプリミティブなことなんだ、って感じるんですよね。これ、インターネットが無い時代だったらどうなってたんだろう、とか。自分で「quartets」観てても「あ、こんな接近して演奏してるのいいな」って思っちゃうんですよね、素朴に。
会田:そうですよね。更に言うと、こんな状況だからこそ、作品にとって観客の身体って何だろう?という問題を考えられる時期でもあるなと思っています。たとえば作品の目の前に自らの肉体を持っていくことの意味。コロナになるまであまり深く考えなかったけれど、今なら考えられる。展覧会を企画しても、密を避けるため、鑑賞の時間や空間を区切る工夫を考えるんです。しかし、そもそも誰かの指示で鑑賞時間を制限される不自由さって何なんだろう?と、改めて考える。鑑賞者の中に流れる時間についてですね。
大友:音楽は、特にライブはオーディエンスがいることを前提にずっとやってきたんで、それが今出来ないなかで、皆配信とかでやってるじゃない?で、何度かやってみたけど、あんまり面白くない。
かつてライブをやっていたような頻度で、配信をやりたいかって言われると、多分やらないと思うんですよ。けど、「quartets online」の話が来たときは、「むしろ、これなら全然アリ」って思ったんですよね。
配信ってなんかフェアな関係じゃ全然ないような気がしていて。変な言い方だけど、配信はワンクッション置いてお互いにただ対峙しているだけだから、その歯がゆさがあるんだけど、この「quartets online」だと、演奏者がリアルタイムに演奏しているのとは違うんですよね。
実際はデジタルのプログラミングが既に録音・撮影されたものを動かしているだけに過ぎないんだけれども、それを、多分オーディエンスと作り手である僕もほぼイコールな環境で観れるので、フェアじゃないって感じがしないんですよね。
同じ音が出てるんだけど、これだったら共有できる何かかもしれないなって感じてて。本当は「配信じゃなくてライブに越したことないよ」っていつも思ってたのが、何ヶ月か色々やってみた末に、初めて配信でこれならアリだって思えた。
会田:少なくとも、なにかの”代替物”としてやってるってこととは全く違う在り方じゃないですか。
大友:そうですね。
会田:例えば、単に喋るという素朴な行為でも、目の前の人に話しかけることの代替物としてラジオがあるわけではない。ラジオはラジオというひとつの身体の在り方がある。DJが不特定多数の聴衆に対して二人称で「あなた」って語りかけるという、ラジオの登場前には想像できなかった身の在り方が形成されていて。それはひとつの新しい身体というか、声と耳との関係が更新されているんです。「quartets online」については、演奏とオーディエンスの新しい関係っていうのをライブ演奏の代替物ではない形で新たに構築できるんじゃないかと。
大友:見事に言ってくれてます。そうだと思います。だから、「あ、これだったら配信、嫌だな」とならず、やっても良いなって直感的に思えた。
最初は立体のインスタレーションを平らな画面に落とすのは、凄い簡単だと思ってたんですよ。俺はただ平面に落とせばいいんじゃないのって普通に思ってたんだけど、作り始めたら、これ簡単じゃない、やっぱり別物なんだっていう、やり始めて初めて気付きましたね。
会田:平川さん、そこらへんは作る前から、どういう風に想定しました?
平川:そうですね、当初はインスタレーションの代替物になる可能性はあったと思いますね。だから、はじめは空間全体が把握できないという空間体験を一枚絵のなかでいかに置き換えるか、みたいなことを考えたりしてたんですけど、いやいやそういうことじゃないっていうのはすぐに分かり始めて、それこそ大友さんがおっしゃるように全く別物になっていくっていうのが分かっちゃいましたね。
大友:そうですね、わりとすぐに別物にしないとまずいなって思いましたよね。思ったより簡単じゃなくて、平川くんの仕事増えるんじゃないかなと思った。
平川:(笑)。そうでしたね。
大友:最初に「quartets online」の試作を見た時に、一体どこから手付けて平面に落としていったらいいのか、すぐには分かんなかった。しばらく眺めてて、「何が問題だろう?」って考えていきましたね。そこで、そぎ落とす方向に進もうというのが一点と、実際よりも画面が小さいというのがこんなに違うというのが二点目。映画の仕事をしながらDVDと見比べて、そのことはよく知ってるはずなのに。
会田:今回作品を体験する環境が全く異なるわけですよね。画面のサイズはiPhoneとかもあり得るし、耳の中に入れるイヤホンなどを使う人も居るはず。インスタレーション版では見えてたはずの、細かくケーブルが揺れる様子などは見えなくなる一方で、耳の中で音が鳴る感覚は生まれたりとか。
大友:音の環境は全く異なってるんですよね。元々8ch、しかもスピーカーの向きがまちまちだから、立ち位置で聞こえ方が変化して本当に豊かだったのが、今回はステレオ2ch。通常のCDと同じになるんですよね。だとすると、むしろ普段僕らがやり慣れている音楽聴取に極めて近くなるから、もう丸っきり、それだけとってもインスタレーションとは全然違うんですよね。
会田:オンライン版にしていくって一言で言うと、簡単そうに聞こえるけど…。
大友:ごめん最初はなめてました。ていうか最初に多分オンライン版やろうって言ったときも、そんなに複雑なことしなくてもいいと思ってたから言えたんだと思うんです。おんなじソフトウェアを平面にすりゃいいんじゃないの、くらいに普通に思ってたんだけど全然そんな話じゃなかった。
平川:出来る限り手数は減らそうと思ってたんですけど、甘かったですね(笑)。
伊藤:僕は絶対こうなると思ってた。とはいえ、この短期間に結構詰めていきましたよね。
大友:うん。音もステレオになって、画面も小さくなって全く異なってしまうとも思ったんだけど、色んなコンセプトはとりあえず一旦忘れて、この自動的に生成される即興演奏と、この影をどう見るのが一番自然だろうって頭切り替えると答えが出てきた感じだった。
伊藤:今回、演奏者の出入りの映像をカットし、画面と音量をフェードさせて登場させるようにしましたよね。あれが凄い奥行きを作ってるなと思って。
大友:インスタレーションの時は、見る/見ないをお客さんに委ねていた演奏者の出入りの音量は、フェードとかしてなかったよね。
平川・伊藤:してないです。
大友:演奏家の出入りの風景はいらないなと思ってカットしたのは、等身大の展示版では自然な人の動きに見えていたものが、小さなスクリーンで、かつ全体が見えてしまう中だと、まるで演出のように見えてしまって、余計な情報になってしまうなって感じたからなんです。ステレオの音楽に接する上ではいらないなと。
平川:僕はあの出入りをカットする、という判断が一番大きかったなと思ってます。出入りを無くして、一人の演奏の長さを最短2分ぐらいまで詰めるていう。その2つの指示で物凄く舵が切れたなっていう。
大友:そうですよね。それが根本的な変換点ですね。普通の録音音源を自分が聴くときにどういう意識で聴いているのか、っていうところから考えてみる。どうあれ音自体は全然面白いわけですから、そこから逆算していって、影の映像がどう見えるのがこの即興演奏を聴くのにいいのかって考え方ですね。
そうやって考え直してみると、これまで展示の際にこだわってたことが大した問題じゃなくなる部分もあったりして。そうして考え直してみることで、むしろ面白い点が顕れる。
「quartets online」のプログラム
会田:平川さん、最後にコンピュータ・プログラムのアルゴリズムについて伺ってもよいですか?
平川:カルテッツなので4人以上が出てこないようになっているんですが、基本的には現在の状態というのを、2秒なら2秒間隔でずっとコンピュータは監視し続けているんですね。もし誰かの演奏が終わったら人数が減るわけなので、次どうしようかと。そしたらサイコロを振るような感じで、誰かが入るとか、もしくは入らないとか、いくつかの選択肢をある確率で割り振っている。その時にたまたま出たサイコロの目に従って動くという感じです。だから前もって何かが決まっているという事はほとんどなくて、その時その時で逐次的に決まっていくという感じですね。誰かが入るとなったら、今登場していないのは誰で、じゃあ誰がいける?みたいなことになって。そうこうしているうちにまた1人抜けて、じゃあ次は誰?みたいなことで、本当にその場の判断でしかないので、絶対に予定調和にはならない。前もってこの人の次にはこの人が来るというふうには決まっていません。その場その場で判断を繰り返して即興的に対処していく。
会田:今の説明を聞いていると、見えないところで、次は誰が出る?ってじゃんけんをしている光景が思い浮かんで面白い。
大友:実際のライブみたいな感じですね。あと、8人の映像も1人につき何種類かあるんですよね。人によって数は異なるし、長さもまちまちだけど。録音録画された量はかなりあり、そのどれが出てくるかっていうのはわからなくて、しかも出るタイミングは毎回違うので、その組み合わせを考えると同じ音の組み合わせの瞬間ってほとんどないはずなんです。だからずっと聞いても飽きなくて、もう十何年もこの作品を見て聞いているはずなのに毎回新しい。
平川:組み合わせだけでできているというのは、AIと比べると明確に違いが出るところですね。AI、機械学習の場合は、いろんな即興演奏から学習して、それっぽい即興演奏を新しく作るっていう手法になると思うんですけれども、「quartets」はそうではなくて、レコーディングされた演奏があって、単にそれが組み合わされていくだけなのに今まで見たことがなかったような表情が出てくる。仮に最終的な結果が同じものであったとしても、手法が持っている意味がAIとは根本的に違うというか。
会田:外側の規範がないということですよね。規範がないけれど、演奏としては完成してしまうという。
平川:機械学習っていうのは、何かを学習したっていっても結局は偽物じゃないですか。一方で「quartets」というのは、どんなことが起きても本物にしかならない。そのバリエーションがほぼ無限にあるということなんです。
大友:演奏した本人たちが意図したアンサンブルではないんです。想像はしていたかもしれないけど、でもどのように組み合わせても、音楽なのか何なのかわからない様々な解釈が可能なものになるっていう面白さかなと思います。
会田:本当にそうですね。ちょうどいい、素敵な締めの言葉になりましたね。本日はありがとうございました。
Artist profile

Photo: Rui Sato
大友良英
音楽家 1959年横浜生まれ。実験的な音楽からジャズやポップスの領域までその作風は多種多様、その活動は海外でも大きな注目を集める。また映画やテレビの劇伴作家としても数多くのキャリアを有する。近年は「アンサンブルズ」の名のもと様々な人たちとのコラボレーションを軸に展示作品や特殊形態のコンサートを手がけると同時に、一般参加型のプロジェクトにも力をいれている。震災後は十代を過ごした福島でプロジェクトを立ち上げ、2012年プロジェクトFUKUSHIMA ! の活動で芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年には「あまちゃん」の音楽でレコード大賞作曲賞他数多くの賞を受賞している。2014年アンサンブルズ・アジアを立ち上げ音楽を通じたアジアのネットワーク作りに奔走。2017年札幌国際芸術祭の芸術監督を 2019年には福島を代表する夏祭り「わらじまつり」改革のディレクターも務めた。

木村友紀
1971年京都生まれ。1996年京都市立芸術大学にて修士課程修了。現在ベルリンを拠点に活動。空間と時間、または次元をテーマにしたインスタレーション形式の作品を発表している。California-Pacific Triennial オレンジカウンティ美術館(ニューポートビーチ、米国、2017年)、「OCEAN OF IMAGES: NEW PHOTOGRAPHY 2015」 ニューヨーク近代美術館(2015年)、第30回サンパウロ・ビエンナーレ(2012年)等、国内外で活動の場を広げている。
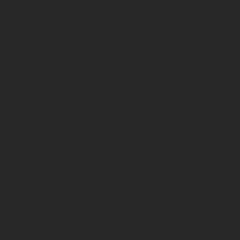
平川紀道
1982年生まれ。もっとも原始的なテクノロジーとして計算に注目し、コンピュータプログラミングによる数理的処理そのものや、その結果を用いたインスタレーションを中心に、2005年から作品を発表。2016年、カブリ数物連携宇宙研究機構のレジデンスで作品「datum」シリーズの制作に着手、豊田市美術館、札幌国際芸術祭プレイベントなどで発表したのち、17年、チリの標高約5000mに位置するアルマ望遠鏡のレジデンスを経て、六本木クロッシング2019などで最新版を発表。また池田亮司、三上晴子らの作品制作への参加、ARTSATプロジェクトのアーティスティックディレクション等も行う。2019年より札幌を拠点。

石川 高
宮田まゆみ、豊英秋、芝祐靖各氏に師事し、雅楽の笙と歌謡を学ぶ。1990年より笙の演奏活動をはじめ、国内、世界中の音楽祭に出演。雅楽団体「伶楽舎(れいがくしゃ)」に所属し、雅楽古典曲や現代作品を数多く演奏してきた。笙の独奏者としても、様々な音楽家、作曲家と共に活動し、即興演奏も行う。 今までに、大友良英、坂本龍一、藤枝守、大森俊、Julio Estrada、Evan Parker、Bozzini Quartet、Antoine Beuger、Magnus Grandberg、Giorgos Varoutasらのプロジェクトに参加。和光大学、学習院大学、九州大学、沖縄県立芸術大学にて非常勤講師、朝日カルチャーセンター新宿教室で「古代歌謡講座」を担当している。

一楽儀光
2012年長年プロとして活動してきたドラムを引退後、tkrworks社ROLAND社ベスタックス社と開発を進めた「doranome」「LaserGuiter」を発表し話題となる。近年では自作モジュラーシンセ「レーザーモジュラー」を開発し世界各地でライブやワークショップを展開すると同時にGIGANOISE、GIGAMODULAR、GIGADISCO等のフェスティバルを企画し世界中で開催している。ARS Electronica Digital Musics部門 Honorary Mentionを受賞しベネチアビエンナーレ、サラゴサ万国博覧会に招待。昨年には瀬戸内芸術祭にて3作品をキュレーションし話題を呼んだ。山口在住。

ジム・オルーク
1969年生まれ。ミュージシャン、プロデューサーとしてポップスからノイズミュージックまで幅広く活動し、「ガスター・デル・ソル」「ソニック・ユース」といったバンドにも在籍。主なソロ作品は『ユリイカ』、『アンシグニフィカンス』など。また、映画においてもリチャード・リンクレイター監督『スクール・オブ・ロック』といった作品の映画音楽を手掛けるほか、00年には青山真治監督作品『EUREKA』に同タイトルの楽曲を提供している。

カヒミ・カリィ
ミュージシャン、文筆家、フォトグラファー。フランスのサラヴァレーベル50周年アルバム「50ans de Saravah」参加。エッセイ『小鳥がうたう、私もうたう。静かな空に響くから』(主婦と生活社)、フランスの絵本翻訳『おやすみなさい』(アノニマ・スタジオ刊)。 アメリカの書籍翻訳「サンタへの手紙」(クロニクルブックス・ジャパン)。2018年、自身の子育て記録『にきたま』(祥伝社)など。雑誌『veggy』でフォト&エッセイ連載。NY在住。 長い海外生活の中で医食同源な生活の日々を綴ります。

Sachiko M
sinewaves、即興演奏家、作曲家。2000年発表『Sine Wave Solo』のミニマリスティックなサウンドで世界の注目を一気に集める。2003年『アルスエレクトロニカ・ゴールデンニカ賞』受賞。海外フェスティバルでの演奏、サウンドインスタレーションなどを行う中、ドラマ『あまちゃん』劇中歌“潮騒のメモリー”(共作:大友良英)の作曲をきっかけに作曲活動を開始。「音楽」と「美術」の間に切り込む『OPEN GATE』のキュレーション&ディレクションなど、新たな可能性を試み続けている。

アクセル・ドゥナー
1964年ドイツのケルン生まれ。ケルンの音楽学校で、マルト・バーバと共にピアノとトランペットを学ぶ。 1994年、ベルリンに移住。「即興音楽」、「作曲された現代音楽」、「ジャズ」、「電子音楽」の分野で数多くの国際的に知られる人物と協働する。自ら生み出したテクニックをベースに独自のトランペット演奏スタイルを確立し、しばし稀なスタイルの演奏を行う。ヨーロッパ、南北アメリカ、アジア、アフリカ、オーストラリアでのコンサートツアーを実施。多数のCDおよびレコードリリースでの出演を行なっている。

Photo: Alessandro Albert
マーティン・ブランドルマイヤー
1971年、オーストリア バート・イシュル生まれ。即興と作曲の間、および電子とアコースティック音楽の交差点で活動。ドラマーとして、実験的な手法と拡張されたテクニックをグルーブと組み合わせた独特のスタイルで広く知られる。90年代後半から グループPolwechsel、Trapist、Kapital Band のメンバーであり、1997年に設立されたTrio Radianを通じて主に国際的に知られるようになる。1990年代後半以降、Radianと共に7枚のアルバムをリリース、そのうち5枚は米国のレーベルThrill Jockeyからリリースされている。 数多くの有名なレコードレーベルで出版。2018年、彼のラジオ番組「Vive lesfantômes」でKarl Sczuka賞を受賞。
大友良英(音楽家):インスタレーション版の「quartets」は、もう12年前になるんですよね。構想からすると13、14年前。普通、音楽はエンディングが必ずあるけど、この作品は、始まりはあるけれど終わらず、どこかでこの人たちはずっと演奏し続けているというイメージがあったので、当初から伊藤さんとウェブ版でできないのかなという話はしていましたね。けれども、忙しかったり、わざわざそれをやるための機会がなかったのでそれきりになっていました。展示は他で2回やったのかな。